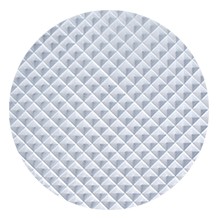江戸切子の日(7月5日 記念日)
東京都江東区亀戸に事務局を置き、業界の発展を促進することを目的に活動する東京カットグラス工業協同組合(現:江戸切子協同組合)が2008年(平成20年)に制定。
日付は江戸切子の文様の一つ「魚子(ななこ)」から「なな(7)こ(5)」と読む語呂合わせにちなむ。
代表的なカットパターンが10数種類あり、「魚子」は魚の卵をモチーフにしたもので、職人の技量を試される難しい文様である。職人技の思いと、江戸切子を多くの人に知ってもらうことが目的。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
江戸切子(えどきりこ)とは、江戸時代末期から江戸、東京都において生産されているガラス細工である。日本での製作は1834年(天保5年)に、江戸大伝馬町のビードロ屋・加賀屋久兵衛(通称:加賀久)が金剛砂を用いてガラスの表面に彫刻で模様を施したのが始まりと言われている。
1873年(明治6年)、品川興業社硝子製造所(現在の品川区北品川4丁目)が開設され、1881年(明治14年)には切子(カット)指導者として英国人エマニュエル・ホープトマンを招き、十数名の日本人がその指導を受け、現代に伝わる江戸切子の伝統的ガラス工芸技法が確立された。イギリスは当時最先端の技術を持っていた。
この頃からカット技術の進歩とガラス器の普及により、切子が盛んに作られるようになり、大正時代になるとカットグラスに使われるガラス素材の研究や、クリスタルガラスの研磨の技法が開発されるなどして、江戸切子の品質はさらに向上していく。
大正時代から昭和初期にかけて工芸ガラスといえば「カットガラス」と言われるほど急速に、かつ、高度の発展を遂げ、日本における第一次の全盛時代を迎えた。そして、江戸切子は1985年(昭和60年)に東京都の伝統工芸品産業に指定、2002年(平成14年)には国の伝統的工芸品にも指定されるに至った。
江戸切子の将来としては、かつてないガラス工芸発展の時代に、美しさと品質を追求したガラス工芸品として江戸切子の伝統を長く保存育成することを目指している。