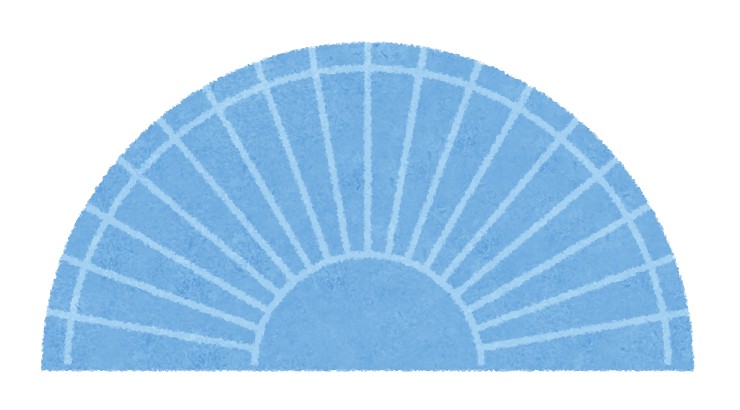円の1周が360度になった理由
現在では円の1周は360度となっているが、これは1年がだいたい360日だったことに由来している。このことは古代の人が考えた結果である。
古代バビロニアの人々が農作業を効率的に行うために1年をはかったのが始まりである。紀元前3500年ごろ、チグリス川とユーフラテス川の流域に世界四代文明の一つであるメソポタミア文明が誕生した。古代バビロニアの人々がメソポタミア文明の基礎を築いた。
メソポタミア文明では農作業に活用するために天文学や数学が発達していた。当時の人々は種まきや収穫の時期を知るため、または洪水の被害を避けるために暦(こよみ)を使うようになった。もともと使っていたのは太陰暦だった。
太陰暦は月の満ち欠けで1ヵ月を定める方法である。新月から満月まで約15日、満月から新月に戻るまで約15日で、1ヵ月は29.5日だった。しかし、この方法だと1年が354日になってしまい、少しずつ季節と暦がずれてしまう。
今でこそ1年は365日と分かっているが、当時は分かっておらず、太陰暦で1年をはかると太陽暦よりも11日短くなってしまう。1年で11日ずれ、3年で33日ずれ、1ヵ月分以上のずれになってしまう。そこで目をつけたのが太陽の動きである。
古代の人々は太陽が地球の周りを回っていると考えていた。毎日、太陽がどこからのぼるか位置を記録した。日の出前に同じ場所へ足を運び、太陽がのぼる位置を地道に記録し、調査を進めた。当時の記録として、昼の長さと夜の長さが同じ日を春分の日と定めた粘土板が残っている。
そして、当時の人々は太陽がのぼる位置がだいたい360日で元に戻ることを確認し、これを1年とした。この時すでに1年は365日だと気づいていたはずだが、360日はとても便利で奇跡の数字だった。
現在の一般的な計算方法は10ずつで位を1つあげる10進法だが、古代バビロニアの人々は60ずつで位を1つあげる60進法を使って計算していた。当時はくさび形文字で数字を表し、1~60の数字を表記していた。今でも使われている1分が60秒や1時間が60分というのも当時の60進法に由来している。
360は60進法の60でも割り切れ、12ヵ月の12でも割り切れるため、とても計算がしやすかった。他にも1~10の数字のうち7以外の数字で割り切れる。こうして古代バビロニアの人々は1年で地球の周りを回る太陽を便利な数字の360で分割した。そして、1日分の太陽の動きの単位を1ウシュとした。この1ウシュが単位の角度1度の始まりである。
古代の人々はウシュ(角度)を土地の計測や計算に応用した。円の1周360度が世界に広まったのは紀元前600年ごろの古代ギリシャの時代で、哲学者・数学者のタレスたちが60進法とともに円の1周360度を数学の世界に導入したのがきっかけである。そして、便利な数字の360度は現在でも使用され続けている。
リンク:Wikipedia
2025/8/21
カテゴリー「生活・科学」