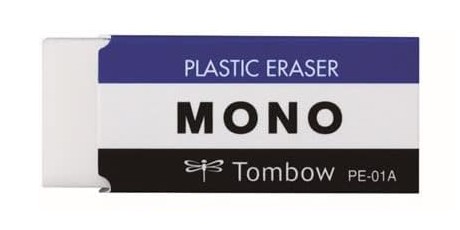消しゴムが紙のケースに入っている理由
消しゴムは普通紙のケースに入っているが、これは周りのプラスチックとくっつくのを防ぐためである。消しゴムの歴史とともに確認してみる。
消しゴムが誕生したのは1770年のイギリスでのこと。それまで鉛筆の文字は固くなったパンで消していた。イギリス人化学者ジョゼフ・プリーストリー(Joseph Priestley、1733~1804年)が天然ゴムに鉛筆の文字を消す性質があることを発見し、消しゴムが誕生した。なお、発見日とされる4月15日は「消しゴムの日」(Rubber Eraser Day)となっている。
消しゴムは鉛筆文化だったヨーロッパやアメリカへ広まり、日本に消しゴムが伝わったのは明治時代初期である。それまで日本は墨と筆で文字を書く毛筆文化だった。ヨーロッパやアメリカの教育の仕組みを取り入れる中で、同時に鉛筆と消しゴムを使うようになった。
その時の消しゴムはまだケースに入っていなかった。当時はアメリカなどからの輸入に頼っていたが、日本国内でも製造されるようになった。しかし、消しゴムの原材料となる天然ゴムは島国の日本では輸入が不安定で、価格や品質が安定しなかった。また、天然ゴムの消しゴムは消えも悪く、力を入れすぎて紙が破れることも多かった。
低価格で安定した消しゴムを供給するためにも天然ゴムの代わりとなる材料を見つける必要があった。試行錯誤の末に誕生したのが私たちが今でも使っているプラスチックの消しゴムである。1950年代中ごろに世界初のプラスチック消しゴムが日本で誕生した。
天然ゴムの消しゴムの代わりを探す中で、ポリ塩化ビニルに鉛筆の文字を消す性質があることが分かった。塩化ビニルは合成樹脂(プラスチック)の一種で、加工がしやすく耐久性も高いという特徴があった。塩化ビニルの用途として、水道管や長靴、バッグなどが挙げられる。
また、塩化ビニルの原材料は主に石油と塩で天然ゴムよりも安く作れた。天然ゴムの加工には1週間ほど時間がかかっていたが、塩化ビニルの加工は2~3日しかかからず、コストと製造時間ともに削減することができた。
このプラスチック消しゴムが生まれたことで、紙のケースに入れられることとなる。プラスチック消しゴムで文字が消える理由は3つの原材料にある。大部分を構成する鉛筆の黒鉛を吸う性質がある石油由来の塩化ビニル、その塩化ビニルを軟らかくして黒鉛の吸着力をアップさせる軟化剤、黒鉛を消しカスとして排出しやすくする充填剤で出来ている。
これら3つの原材料によってプラスチック消しゴムで文字をこすると、黒鉛を吸収し、消しカスとして排出し、文字を消すことができる。よく文字が消えるようになった一方で、時間が経つとプラスチックの引き出しやペンケース、下敷きなどとくっつく問題があった。その原因が軟化剤の移行性である。
軟化剤の移行性とは、同じ石油由来のモノに触れ続けると軟化剤が相手に移動するという性質である。消しゴムの中の軟化剤は塩化ビニルとは完全に混ざっておらず、時間が経つとしみ出し、多いほうから少ないほうに移動し、相手のプラスチックを軟らかくして絡みついてくっつく。
そこで登場したのが紙のケースである。消しゴムを紙のケースに入れると軟化剤の移行が発生しない。軟化剤は同じ石油由来のモノと長時間触れると移行するが、石油由来でない紙の素材の場合は移行が起きない。また、紙は安価で加工がしやすいという特徴もある。
1960年代後半にプラスチック消しゴムに紙のケースが付くようになった。このように消しゴムが紙のケースに入っているのは、周りのプラスチックとくっつくのを防ぐためである。その他にも、紙のケースには消しゴムを折れにくくする効果もある。
関連記事
2025/8/8
カテゴリー「生活・科学」
関連記事