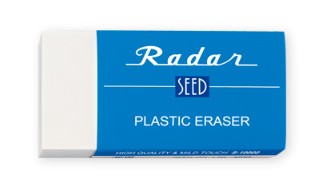消しゴムの日(4月15日 記念日)
1770年にイギリス人化学者ジョゼフ・プリーストリー(Joseph Priestley、1733~1804年)がブラジル産の天然ゴムに紙に書いた鉛筆の文字を消す性質があることを発見し、消しゴムが誕生した。
その発見日とされる4月15日が「Rubber Eraser Day」(消しゴムの日)となっている。記念日を「National Rubber Eraser Day」として、2018年(平成30年)にアメリカで初めて祝われたとの情報も見られる。消しゴムの発明を祝い、人々に消しゴムをもっと使ってもらうことが目的。
イギリスで消しゴムが発明されるまで鉛筆の文字は固くなったパンで消していた。1772年頃にはロンドンで消しゴムが市販されており、「rub out(こするもの)」と呼ばれた。これが今日ゴム一般を意味する英単語ラバー(rubber)の語源である。
ラバー(rubber)はゴムやタイヤなどの意味があり、主にイギリスでは消しゴムの意味でも使われる。一方、主にアメリカでは消しゴムはイレイサー(eraser)と呼ばれる。
消しゴムは鉛筆文化だったヨーロッパやアメリカへ広まり、日本に消しゴムが伝わったのは明治時代初期である。それまで日本は墨と筆で文字を書く毛筆文化だった。ヨーロッパやアメリカの教育の仕組みを取り入れる中で、同時に鉛筆と消しゴムを使うようになった。
1886年(明治19年)に東京の町工場・三田土ゴム製造株式会社で日本で初めての国産の消しゴム製造が始まった。その後、各社参入し改良が加えられ、1959年(昭和34年)に日本のシードゴム工業(現:株式会社シード)がより消去性に優れたプラスチック字消しを開発し、以後その性能から市場の主流となる。
日本は島国であり原材料の天然ゴムの輸入が不安定で、価格や品質が安定しなかったことがプラスチック消しゴムの誕生に起因している。天然ゴムは紙ごと削ることによって文字を消す「砂消しゴム」などの特殊用途の品を除き、原材料として現在はほとんど使用されていない。
プラスチック消しゴムは、主に石油と塩で作られるポリ塩化ビニルが原材料で、天然ゴムの消しゴムに比べて文字がよく消える。その一方で、時間が経つとプラスチックの引き出しやペンケース、下敷きなどとくっつくという問題があった。
その問題を解決するためにプラスチック消しゴムは紙のケースに入れられる。紙は安価で加工がしやすいという特徴がある。消しゴムを紙のケースに入れることで、消しゴムが周りのプラスチックとくっつくのを防ぐことができる。また、紙のケースには消しゴムを折れにくくする効果もある。
関連する記念日として、「文具と文化は歴史的に同じ意味をもってきた」ということから「文化の日」の11月3日は「文具の日」、1886年(明治19年)5月2日に日本初の鉛筆の工場生産が始まったことに由来して5月2日は「えんぴつ記念日」となっている。
関連記事