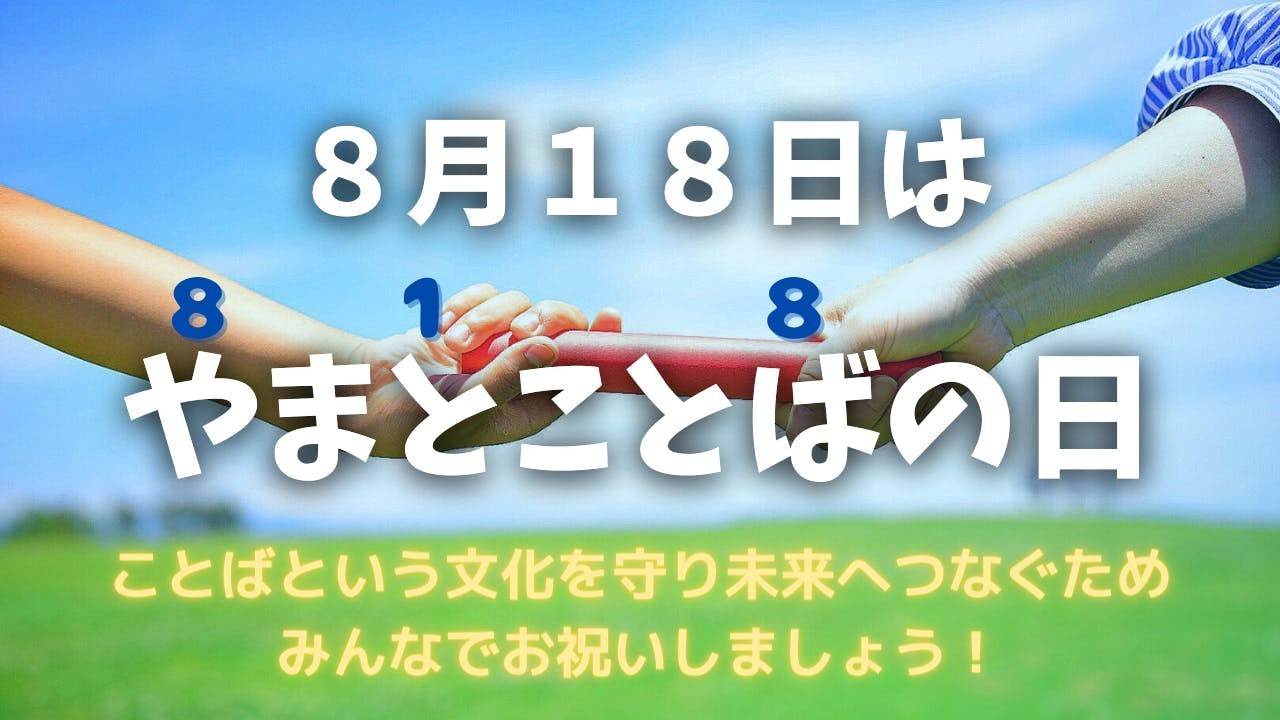やまとことばの日(8月18日 記念日)
大阪府八尾市に代表を置く「うまし国やまとことばの会」が制定。
日付は「や(8)まと(10)ことば(8)」と読む語呂合わせで8月18日を記念日としたもの。クラウドファンディングにより多くの賛同を集めて誕生した。
自然と調和し豊かに生きる心を育む「やまとことば」という古来から使われてきた日本独自の言語を、日本文化とともに守り継承し伝えていくことで、子どもたちがありのままの自分を肯定できるように育ってほしいとの願いが込められている。
記念日は2024年(令和6年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。これを記念して同年8月18日(日)の「やまとことばの日」に日比谷図書文化館・日比谷コンベンションホール(大ホール)にてお祝いのイベント「やまとことばまつり」が開催された。
「やまとことば」は漢字や外来語が入ってくるずっと前から、古いものは1万6千年前の縄文時代から使われてきたものとも言われている。漢語や外来語に対して日本語の固有語とされる言葉のことで、和語(わご)とも言う。漢字には音読みと訓読みがあり、訓読みにあたるものの多くが実は「やまとことば」である。
例えば、みる(見る)、はなす(話す)、よい(良い)、が(主格の助詞)、うみ(海)、やま(山)、かわ(川)、さくら(桜)、はれ(晴れ)、あめ(雨)、ゆき(雪)、め(目)、はな(鼻)、くち(口)、おはよう、こんにちは、いただきます、あした(明日)、ゆ(湯)などが挙げられる。
一方で、山川(さんせん)、草原(そうげん)、晴雨(せいう)、雪(せつ)、生物(せいぶつ)、風車(ふうしゃ)、色紙(しきし)、学習(がくしゅう)、報告(ほうこく)、連絡(れんらく)、調査(ちょうさ)、決定(けってい)、集合(しゅうごう)、確認(かくにん)、速度(そくど)などの読み方は外来語で、中国で当時話されていた言葉である。
「やまとことば」は一音一音に意味があるという、世界でも珍しい言語である。「やまとことば」の特徴の一つには母音が中心ということがある。どの音も長く伸ばすと「あいうえお」のいずれかの音になる。また、発声の仕方や語感がそのまま意味をつくっている。
例えば、「あ」は口を大きく開いて発声するから、開く意味。開く(あく)、明ける、明るいなどの言葉がある。「う」は口を閉じて発声するから、閉じる意味。また「う~」と力をためるところから「生み出す」という意味も持つ。生む、うなる、受ける、内などの言葉がある。
その他、「い」は生命や活動、強さという意味があり、息、生きる、命、今などの言葉がある。「え」は分岐や分かれて伸びるという意味があり、枝、江、選ぶなどの言葉がある。「お」は偉大や重要という意味があり、大きい、多い、奥、重いなどの言葉がある。
全ての音にこれらの意味が込められているので、日本語を話す人は音に対して情緒豊かになることが分かっている。例えば、秋に虫の声を聞くとしんみりするが、これは日本語話者の脳の使い方によるものという研究結果がある。話すことで心が自然と調和する。実は私たちは「ことば」によって文化も受け継いでいるのである。
関連する記念日として、「こ(5)と(10)ば(8)」と読む語呂合わせから5月18日は「ことばの日」、5と10で「五十音図」の「五十」に当てはめて5月10日は「五十音図・あいうえおの日」となっている。
関連記事