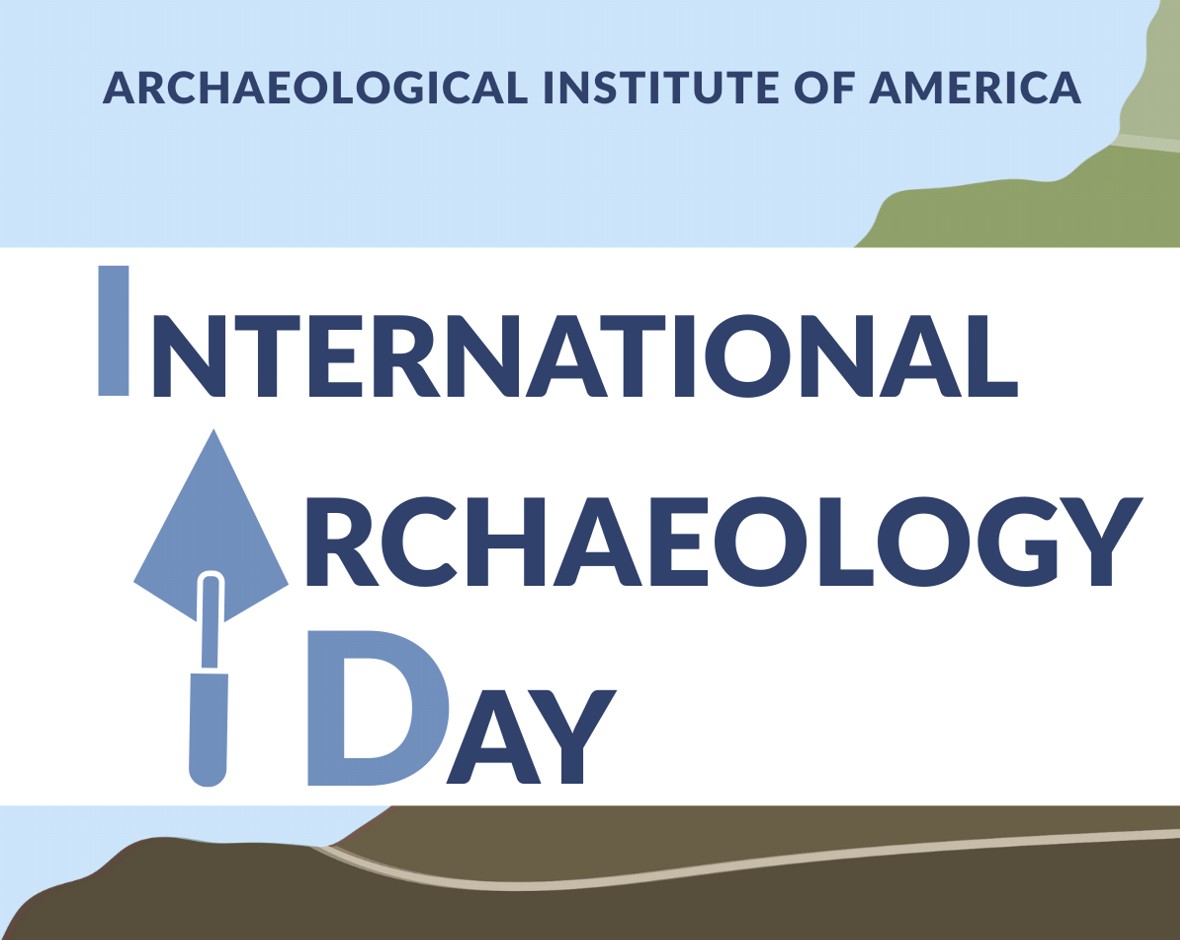国際考古学の日(10月第3土曜日 記念日)
アメリカにおいて考古学を研究する組織「Archaeological Institute of America」(AIA)が2011年(平成23年)に制定。
記念日の英語表記は「International Archaeology Day」(IAD)である。「archaeology」(アーキオロジー)は「考古学」の意味。この日は遺産や文化財を発掘・調査し、過去を学ぶ考古学という学問に敬意を表する日。また、考古学とその社会への貢献を祝う日である。
日本ではあまりなじみのない記念日だが、この日には大人から子供まで考古学に関心を持つ人々のために、遺跡を巡るツアーや模擬発掘の体験会、講演会など様々なイベントが開催される。FacebookやXなどSNSでは「#IAD2025」のようなハッシュタグを使用して記念日が祝われる。
「国際考古学の日」(10月第3土曜日)の日付は以下の通り。
- 2024年10月19日(土)
- 2025年10月18日(土)
- 2026年10月17日(土)
記念日を制定した組織「AIA」の日本語訳を「アメリカ考古学協会」や「アメリカ考古学研究所」とするものが見られるが、「アメリカ考古学協会」はアメリカにおける考古学の専門家の組織「Society for American Archaeology」(SAA)を指す言葉でもある。
考古学とは、人類が残した遺跡から出土した遺構などの物質文化の研究を通し、人類の活動とその変化を研究する学問である。対して、歴史学は、文字による記録・文献に基づく研究を行う。
「考古学」を意味する「archaeology」という言葉は、古代ギリシャ語の「古い」と「言葉・学問」に由来する。日本語の「考古学」(考古)という言葉は、明治初期には「古き物を好む」という意味で「好古」と記されていたが、「古きを考察する学問」だという考えから「考古」と記されるようになった。
関連する記念日として、「大森貝塚」を発見・発掘したアメリカの動物学者エドワード・S・モース(Edward Sylvester Morse、1838~1925年)博士が来日した1877年(明治10年)6月18日に由来して、6月18日は「考古学出発の日」となっている。
また、竪穴式住居跡から日本最古の「おにぎりの化石」が発見された石川県鹿西町(ろくせいまち、現:中能登町)が制定した記念日として、同じく6月18日は「おにぎりの日」となっている。